2004年11月22日  |
2005年10月1日 |
2005年第2回コンサートのプログラム(右上)に拙文を載せていただきました。
HP掲載にあたり加筆修正、写真を加えて再構成しました。
−びぃの部屋−<びぃのプチギャラリー>
Franco Corelli フランコ・コレッリ
フランコ・コレッリ(1921−2003)は、20世紀後半を代表するイタリア人テノールの一人です。
2004年と2005年、マエストロに捧げるメモリアル・コンサートが
熱狂的崇拝者であるオペラ研究家のプロデュースにより東京で開かれました。
2004年11月22日  |
2005年10月1日 |
| フランコ・コレッリ、歌うことは生きること 「人は子どもに向かって成熟する」という言い方があるそうだ。すると私は幸運にも、偶然の出会いに恵まれて、子どもの頃の思いをたどりなおす機会を与えられている。 私は幼い頃お絵かきばかりしていた。小学校では集団になじめず同級生たちを眺めていることが多かった。6年のとき、トーマス・マンの『ヴェニスに死す』を読み、美少年に心奪われる老作家に感情移入して「私は美を讃えるために生まれてきたんだ」と、ひとつ自分がわかったように思った。 1971年、中学2年の秋の夕、運命の出会いはテレビからいきなり飛び込んできた。 <フランコ・コレルリ初来日リサイタル> 部活から帰り茶の間に入ったとたん、その横顔、その容姿、立ちふるまい、まさに私の <理想の男性美>がそこにあった。ファザコン娘には、三十いくつの年の差もかえって好ましく、兄が愛読していた『音楽の友』『レコード芸術』から写真を切り抜いてはクリアケースにおさめ、いつも持ち歩いた。グループサウンズの人気アイドルに入れあげる友人たちもあきれていたようだ。 当時の私は、家や学校で成績の良い兄のことばかり話題にされるのでかなり鬱屈していた。学校では<コレルリさん>の写真をよりどころにし、帰宅すれば自室にこもり数少ないレコードに何度も針を落とした。すると次第に、輝かしい姿と歌声の奥にある、彼の繊細な魂、深い孤独が聴こえてきた。テノールにしては明るすぎない声質で豊かに響く中音域や、夜の闇を薄く切り進む一条の光のような、高音部の果てしないディミヌエンドに憂いを重ね、最高音での鮮烈な立ち上がりと熱情のほとばしりに、抑圧された自分のこころを解放していたのだろう。 ( 詳しくは、びぃのもう一つのサイト<めぽっく21>→<こころのリハビリ>自分のことを話しましょう その2 <居場所がない> をご覧ください ) 1973年、高校1年の9月、再来日を知り、親にコンサートに行きたいと頼んでみた。チケットは1枚6,000円。当然父にはダメだと言われて、次の手に出た。中間テストを休めば、教育ママの母が折れるだろうと踏んだ。案の定、一日休んだだけで、「お父さん、私が付き添うから行かせてやりましょう」 11月、母に連れられ、NHKホールで <レナータ・テバルディとのジョイントコンサート> 舞台の左袖から、長い脚が一振り蹴り出された瞬間、もう ぼお 数日後、一人で銀座の楽器店で行われたサイン会へ

「コレッリ!」 サイン会が終わってもごった返す店内で、テバルディさんがそう一声高く呼ぶのを耳にして、実際の発音は、当時の日本語表記<コレルリ>と違うことを知った。 1975年、高校3年の春、進路を決めあぐねていた私は、大好きな『トロヴァトーレ』(トーマス・シッパーズ盤)を自室で聴いていた。それまではコレッリさんの十八番、マンリーコの歌声に全曲通して聴き惚れていたのだが、その日はなぜか、第2幕、アンヴィル・コーラスに続くジュリエッタ・シミオナートさんの♪炎は燃えて♪ に惹きつけられ・・・ 突然、自分が部屋もろとも燃え上がるかのような錯覚に陥った。興奮さめやらぬまま、オペラっていいな、大学ではイタリア語を学ぼう、そう決めた。 それからはるかに時は経ち、1998年、四十代最初の元旦。 大晦日から、「コレッリさんに導かれて、二十代はイタリアといろいろ縁があったけど、三十代は子育てと親の世話でイタリアがずいぶん遠くになっちゃったなぁ」と嘆きつつ、実家で寝ぼけ眼をこすりながら広げた朝刊には、オペラ特集、酒井章さんの『イタリア派は歌を楽しむ』・・・「オペラに目覚めたのは、フランコ・コレッリの歌うアリア集」 えっ、ホント!!? 新聞記事から104番で電話番号は簡単にわかり、思い切って電話した。酒井さんは突然のぶしつけな相手に、 「批評家には叩かれ続けましたが、昔も今も世界中のテナーが憧れるテナーです」 「今年、生まれ故郷のアンコーナで彼の名前を冠した国際声楽コンクールが始まりま す」 「ホームページもありますよ」と矢継ぎ早。ファンクラブの楽しさを知った。 コレッリ・ホームページを開いていたのは、アンコーナ市『オペラ友の会』芸術顧問で、コンクールの審査員でもあったアレッサンドロ・ショッケッティさん。久しぶりにイタリア語の辞書を引き、自己紹介とコンクール開催のお祝いをしたためてメールを送った。 何度かやりとりしているうちに、「このコンクールの記事を日本で目にしたことがありますか?」と訊かれた。 「日本でも宣伝してもらいたいようですよ」と酒井さんに伝えると、「わかりました、任せてください!」ときっぱり。 翌日、 「日本語のチラシを用意すれば、コンサートのプログラムに無料ではさみこんでもいい という興行主がいるのですが・・・」 「私が作ります!」
第1回大会の参加者は約180人(うちテナー70人)とコンクールは大成功。実際に現地に赴いた酒井さんによると審査委員長のコレッリは、本選前から精力的に若手歌手を指導し、わざわざ席を立って助言する場面もあったそうだ。ソプラノの佐藤美枝子さんが入賞し、同年チャイコフスキー国際音楽コンクール声楽部門で優勝している。 翌年第2回のチラシは、ショッケッティさん、酒井さんに早めに連絡を取り、余裕があったので前回印刷を頼んだ知人に、コンクール募集要項と同じ体裁、写真で版下から作ってもらった。 東京芸術大学新奏楽堂では、開場前に外で待つお客さんたちに、「イタリアで開かれるコンクールですが、お知り合いの若手歌手に参加をおすすめください」と声かけしながら、酒井さんとチラシを配った。このとき観た卒業公演『こうもり』は、みなさん芸達者でノリがよく、オペレッタを十二分に楽しめた。中島康晴さんのアルフレードも聴けた。彼はこの年のコンクールに参加、惜しくも優勝は逸したがマエストロ・コレッリに絶賛されたという。
第3回の2000年は、実家で父の病後を看ている最中だった。どうにか刷り上ったチラシを見て愕然とした。パソコンでなくファックスで受け取ったゲラでは写真の縦横縮尺の違いを見落とし、コレッリ扮するカラフの顔が横広がりになってしまった。 今でも痛恨のチラシだが、手元の一枚には<Franco Corelli Ancona 10-6-2000>のサインが入っている。これは、ファン仲間のなつ さんが、カフェテリアで「マエストロ!日本でチラシを作った友人がいます」と本人を呼び止めてもらってきてくれたものだ。
残念ながらコレッリ・コンコルソは3回で終わってしまったが、酒井さん、ショッケッティさんとの共同作業、チラシを仕上げ、配るまでにいただいたさまざまなご厚意、そしてなつさんの心配りは忘れられない。 学生時代、イタリア文化会館館長の16歳のお嬢さんが、”L'amore del cristiano e' l'agire.”「キリスト者の愛とは、行動すること」と教えてくれた。 真の芸術にも、人を行動へと駆り立てる力がある。 イタリアでのコレッリ情報を和訳紹介している なつさんのHP ( なつのイタリア文化周遊 →フランコ・コレッリに捧ぐ)から、2003年深秋、パルマの新聞 『Gazetta di Parma』が組んだ追悼特集より、アルトゥーロ・トスカニーニ財団ジャンニ・バラッタ監督の哀悼のことばを引用させていただく。 「フランコ・コレッリと会うと、我々の話題は常に若い世代に関するものとなりました。つまりオペラの将来は、次世代のアーティスト育成の分野に長期的な責任がかかっているのですから。彼は若者たちに大きな関心を抱いていました。コレッリが教育者としても大いなる責任を持って、教えていたことを忘れてはなりません。アーティストとしての活動だけでなく、人格形成という面での音楽教育に関心を持ってトスカニーニ財団の活動と発展に従事していました」 酒井さんはこれまでも若手デビューに力を貸していたが、アンコーナのコンクールでコレッリと直接会ってからその思いを深くし、一周忌にあたる2004年から、この『フランコ・コレッリ メモリアル・コンサート』を毎年開催する決意をした。 私はチラシを配る間に、海外のコンクールに参加するのに何から何まで自分で手配しなければならない日本の若者たちの苦労と、必ずしも若手育成に熱心ではない大歌劇団の実態を垣間見た。この国の芸術振興策のみすぼらしさを考え合わせると、酒井さん一人の頑張りでは若手研鑽の場はとても足りない。 20年前、中部イタリアの人口5,000人の山村カステル・ディ・サングロで暮らす日本人女性から、「このまちでは、若い人たちが作品を展示するスペースとして広場を開放して、住民は自分たちの楽しみで気に入ったものを買い求めて、そうすることで地元の芸術家を育てている」という話を聞いた。 コレッリは20歳を過ぎてからアンコーナの友人のすすめで歌を歌い始めた。 もしかしたら、あなたのお住まいのまちにも<21世紀のコレッリ>が眠っているかもしれない。 新しい声の発見を楽しみにしながら、若者たちが気軽に練習できるスペースや、 ステージに立てる機会を、あなたのまちに、もっと作ってくださいませんか? 最後に、 歌を志す若い方々へ 完璧主義で自分の美意識を貫いたコレッリだが、心の奥底には他者とつながりたい、理解されたいという強い希求があった。だからこそ聴衆と批評家との間で絶えず揺れ動き(注1)、舞台で失敗することへの恐れ(注2)も相まって、全キャリアを通して舞台恐怖症と格闘した。それでも彼は神を信じ、オペラを愛し、理想を目指して、心を奮い立たせて舞台に上がった。 歌うことは生きること、そして より良く 生きること
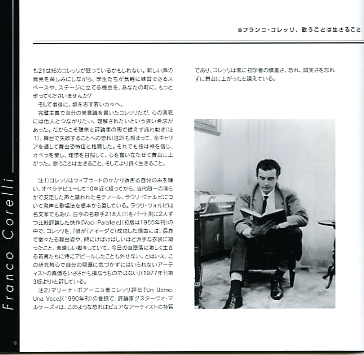 2005年第2回 "フランコ・コレッリ"メモリアル・コンサートプログラム より |
|||||||||||||||||||||||||